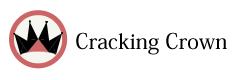「だと思う。死んだことないから分からないけど」
「私もないけど」
テーブルには氷の溶けたアイスコーヒーと水が並ぶ。低いソファ席の下で重ねられた足元には鮮やかな水色をしたエナメル製のヒール。足指には丁寧にひとつずつ色違いのペディキュアが塗られていた。
「あ、それ可愛い」
「でしょ。作ったの」
私の指差したピアスを自慢するように、彼女は髪の毛を耳にかける。砂時計を模したピアスチャームから、こぼれ落ちる砂のように細い金鎖が何本か繋がれている。よくよく見ればチャームとの繋ぎ目にある鎖は不格好に接着されたままだ。
「あ、だめだめ。細かく見られると粗いのばれちゃう」
彼女はあわてて耳にかけていた髪をおろして笑う。髪に隠された耳の先は、わずかに尖っていた。
***
彼女との出会いは、大学の公開講義だった。ゆるく巻かれた黒髪に教室に響くヒールの音、少しレトロなフレアワンピースは雑誌で見た覚えがある。そして淡いすみれ色のフレンチネイルが優雅にペンケースから取り出したのは、ペンキャップのつけられた鉛筆だった。しかも丁寧に赤鉛筆まで揃っている。フレンチネイルはまるで当然のように鉛筆を持ち、すらすらとノートに講義を書き写していく。
休憩時間にカッターで鉛筆を削り始めた彼女の姿に、とうとう私の好奇心が負けた。
削りカスを丁寧にティッシュで包む所作ですら妙に落ち着いていて、そのギャップが余計におかしかったこともよく覚えている。
はじめこそ夜の仕事をしているものだとばかり思っていた彼女は、実はコンビニ夜勤と弁当屋の二重アルバイト生活を送り、それもすべてあのファッションにつぎ込んでいるのだと笑った。鉛筆の理由も至ってシンプルで、構内で配られていたものをそのまま使うのが習慣になっていただけだと言う。それ以外に筆記具を使うことはないからと。
講義で顔をあわせるうちに、講義前に落ち合って近くのカフェでお茶を飲むのも習慣になった。
そのうちに、彼女は真剣な顔で私に告げたのだ。
─ 実は私ね、
****
アイスコーヒーを飲む私の目の前に雑誌を広げながら、彼女は次はこれが欲しいあれが欲しいとページの端を折っていく。まだまだ暑い日が続くというのに雑誌はすでに秋物の特集をはじめていた。栗色のカーディガンに柔らかいシャツ、去年のブーティは気に入っているからまだ使いたいと彼女のおしゃべりは続く。
「バンパネラってそんな流行に敏感なものなの?」
「そりゃそうよ。他にすることないもの」
からかい混じりに言った言葉は真顔で返された。着々と欲しいものリストを挙げていく彼女の姿は、年相応と言えば年相応だ。実際の年齢は『私にも分からない』と濁されている。
学生時代にはそういう設定を持っている子も居た。正直、彼女のこともその類だと思っている。ただ彼女は会話に出せば応じる程度でそれを強いることはない。もっぱら話すことと言えば講義の内容とファッション、それに少しばかりの愚痴と笑い話。私は彼女を、職場以外で出来た友人のひとり、という位置づけに置いていた。
*****
盆休みが近づき、公開講義も終了となる。次の講義はまた秋口からだろう。
いつもどおり、カフェで落ち合い形ばかりのレポートをまとめていると彼女が私に小さな紙包みを差し出した。中をあければ、いつか彼女がつけていた砂時計のピアスだった。
「講義が終わったら、バイトやめて出ようかと思って」
気に入っているというブーティをはいた足を組みながら、彼女が笑う。
「それね、つけなくても良いんだけど誰かに渡したくて。でも、」
つけてくれたら嬉しい、と言う彼女の顔は巻かれた髪に隠れてしまってよく見えない。ピアスの不器量なつなぎ目はいつの間にか改良されていた。揺らせば美しく金鎖がしなる。
「出るって、どこ行くの?」
「そろそろ四国の方が時効だから、あっちなら大丈夫かなって」
「時効って何の」
思わず笑った私を見て、彼女も笑い声を漏らした。
「ちょっと大変なんだから。時間差覚えておかないと、意外と人って人の顔覚えてるものだし」
「派手な服装してるからじゃない」
「そうなの。だから余計に大変」
連絡先の交換をと言いかけた私に、彼女は首を振った。
黒い髪から垣間見える首筋は、ひどく白い。指先も、覗く手首も、まるで日に焼けたことなどないような白さをたたえながら、それでも血管のひとつも浮かんでいない。そういえば彼女は私とカフェで落ち合う中、一度も水を飲むことはなかった。講義中も、講義後も、彼女が何か口に入れた姿を見たことがあっただろうか。
顔を上げれば彼女の姿はすでになく、テーブルにはただ砂時計のピアスが置かれたままだった。
****
宣言通り、彼女は講義を終えてからぱたりと姿を消した。
やがて秋を迎え、また新しい講義が始まる頃になっても。
─ 実は私ね、バンパネラなの
─ そうなの
─ 今の人って本当に驚かないのね
─ そうかもね
彼女の呆れたような笑い声を思い出す。耳につけた砂時計のピアスからはさらさらと金鎖の流れる音がした。
─ じゃあ年は取らないの
─ 多分。そう取ってないと思う
─ でも死ぬには死ぬんでしょう?
─ だと思う。死んだことないから分からないけど
彼女の言葉をすべて信じているかと言えば、それはやはり嘘になる。
きっとまたどこかでコンビニ夜勤と弁当屋の二重生活をしながら、ファッション雑誌にドッグイヤーを作っているのだろうとも思う。
その反面で時々、もし本当に彼女の時間が私とは別に流れていたのだとしたら、とも思う。
けれど、四国まで行くのにかかる時間は彼女も私も変わらないだろう。彼女の時間は私と同じように重ねられているのだ。それがどう作用するのか、何に影響するのかは別としても、私の一日と同じように彼女の一日も進んでいく。そして進んでいく時間の中で、夏の何度かを同じように過ごしたのだ。
その事実は少しだけ、私のこころを慰めてくれた。