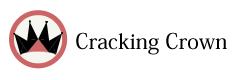もう随分ながいこと歩いてきたのだと思う。少なくとも、彼にとっては。
すっかり擦り切れたローブに穴の空いたブーツ。貧困を課したことなど一度もなかったように思うけれど、敬虔な彼らは余る富は身を滅ぼすのだと、まるで競うようにぼろぼろの衣服を纏っていた。貧しさも富も、結局それ自体は大した理由になどなりはしない。彼らを滅ぼすのはいつでも、彼らなのだ。彼らと似た、彼らとは違う何かを信じる彼らなのだ。
雷が落ちれば森が焼けるように、そして焼けた後には新たな木々が芽吹くように、それは流れゆくものだった。そして私もその流れとともに私の国へ戻り、次を待つのだと。そうなると思っていた。
「天に地に在られる御名の元」
膝を折り、彼は大地に接吻をする。書は左手に抱え、右手は額へ。かつて多くの同胞とともに読み上げた祈祷文を、彼はただひとり続けた。言葉は聞こえぬよう唇の奥にしまいこみながら、彼の祈りは確かに私に聞こえる。
「降る光に、満ちる草木に、明ける日々の歓びを……」
淀みなく続く声なき朗誦が途切れた。彼の祈祷文はいつもこの前後で途切れるのだ。
そして次に続く言葉も私はすっかり覚えてしまった。
「どうかお赦しください、わたしは、」
大地につけたままの額をさらに擦り付ける。
「伝え説いてまわるには、わたしはあまりに脆弱でした」
彼はいつの頃からか私に許しを乞い伏すようになった。
祈りの言葉を止め許しを乞う己をすら責めながら、それでもそれは確かに私に届く。私の芯にある場所を満たしていく。
彼の傍らで肘棒をつき、すっかり薄くなってしまった彼の頭をなでるが私の手が彼に届くことはない。もう少し信徒があった頃にはそれらしい奇跡を起こすことも出来たろうか。今や彼ひとりの祈りで出来上がっている私には、せいぜい彼にもわからない人真似をするしかない。
彼の祈りだけで成り立っている。
彼の祈りだけを聞いて、彼の祈りにのみ満たされる。
なんと贅沢な道があったことだろう。
そしてこれはなんと幸いなることかと、やがて彼が朽ち私の国へ至る時には伝えてやりたい。
お題:信仰